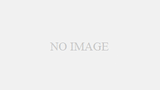花粉症で苦しむ人が年々増えてきています。しかし花粉症そのものが新しい概念であるために、古来の漢方医学には直接的な記載が見当たりません。
そこで、現代の花粉症に対する漢方治療について、実証から虚証まで、また各種の症状パターンに応じた処方を体系的に整理してみました。特に、代表的な10処方について、その使用目標、応用、特徴を詳細に解説し、臨床現場での的確な処方選択の一助となることを目指します。
これにより、古来の漢方医学の知見を現代の花粧症治療に活かす道筋を示すとともに、症例に応じた適切な処方選択の指針を提供したいと考えています。
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3823317202673107"
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- 木もれび鍼灸院サブ -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3823317202673107"
data-ad-slot="9071765140"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>はじめに
花粉症の「証」に基づく漢方処方について、体系的に解説していきます。
花粉症の症状は、鼻閉塞、水様性鼻汁、くしゃみなどを伴う発作で、これらの症状の主要な原因を漢方的に検討すると、水飲が主体となることが多いことがわかります。水飲とは体内の水分代謝の異常を指します。
証による分類
陽証
実証タイプ(体力が充実している場合)
- 越婢加朮湯
目標:体力中等度以上の人。越婢湯証に準じて、浮腫、発汗傾向、尿量減少、口渇がある場合。時に喘鳴、咳嗽、四肢関節の腫脹・疼痛などを伴う。
応用:慢性関節リウマチ、変形性膝関節症、関節痛、鼻アレルギー
説明:朮の働き(水分の停滞をとり、尿利を増し、四肢や関節の痛みを止める)で適応症が広くなった
- 麻黄湯
目標:体力の充実した人、平素じょうぶで風邪をひきにくい人。悪寒、鼻閉塞、発熱、頭痛があり発汗せず、腰痛、四肢の関節痛、筋肉痛などを訴える場合。脈が浮緊で、熱があり、咳もひどい。本方の証は元気な小児(ときに成人にも)には比較的多くみられる。
応用:感冒、流感、上気道炎、乳幼児の鼻閉塞
説明:本方は太陽病(熱病初期)の処方で、桂枝湯の表虚証と対照的な表実証に用いる漢方の代表的な発汗剤である。
中間証タイプ
- 葛根湯
目標:体力中等度の人を中心に用いられる。感冒などの熱性疾患にかかり、主として体表部および身体上部に熱性闘病反応が現われた場合。一般に脈は浮いて力がある。自然に発汗しない。悪寒、発熱、頭痛、項背部のこわばりを訴える。項背強急のある場合は無熱の病気でも用いられる。
応用:感冒の初期、扁桃炎・上気道炎の初期、鼻炎・副鼻腔炎の初期
説明:葛根湯方者ということばがあるくらい、よく用いられ、応用の広い処方で、熱病では初期のうちで、病邪が体表にある太陽病という時期に用いる。
- 葛根湯加川芎辛夷
目標:体力中等度以上の人。鼻閉、鼻漏、後鼻漏などの鼻症状が特に慢性化した場合。葛根湯の証と同じように、しばしば、頭痛、前額痛、肩こり、項背部のこわばりを訴える。一般に脈は浮いて力がある。
応用:慢性副鼻腔炎、急性鼻炎
説明:本方は、葛根湯の加味方。葛根湯と同様に、発汗しやすい人、または虚弱な人には長期使用をしなし。大塚敬節氏は、腹証として臍痛点をみとめる。
- 麦門冬湯
目標:体力中等度の人を中心に。「咳逆、上気、咽喉不利」という。発作性の激しい咳(咳こん)、咽喉部の刺激痛・乾燥感、のぼせて顔面が紅潮するのが目標。痰は粘稠で切れにくいが、切れると咳が一時止まる。また、咳嗽に伴う息切れ、時として悪心、嘔吐、嗄声などを認める。
応用:上気道炎、気管支炎、気管支喘息
説明:妊娠中あるいは高齢者の喘嗽、単なる口腔・咽喉内の乾燥にも用いられる。本方の目標は、下から突き上げる症状を伴うもので、咳ばかりでなく、吃逆、上気による嘔吐、めまいなどがあるものにもよい。
- 小青竜湯
目標:体力のやや低下した人ないし中等度の人。咳嗽、喘鳴、呼吸困難、浮腫、鼻症状などがある場合。泡沫水様の痰や、水様鼻汁、くしゃみを伴うことが多い。呼吸困難がないときは、上腹部の両側直直筋に軽度の緊張があり、時に心下部に振水音を認める。
応用:気管支喘息、喘息性気管支炎、気管支喘息、感冒、鼻炎、鼻アレルギー
説明:気管支喘息では、発作時以外にも用いられる。ただし、麻黄が主薬である本方は、やせて顔色が悪く胃腸の弱い人には使用しないほうがよい。浮腫と喘息が強い証には、石膏を加えて用いるとよい。
虚証タイプ(体力が低下している場合)
- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
目標:体力がやや低下ないし中等度の人。冷え症の人の血行障害、くしゃみ、下腹部、腰部、四肢末端の痛みや冷感を訴える場合。腹証の特徴に、下腹、鼠径部の付近に、斜めにふれる索状物があり、触診に圧痛を訴えるものがある(大塚口訣)。また、下痢を伴ったり、頭痛、頻尿などのあることもある。
応用:冷え症、坐骨神経痛、腰痛、凍瘡、腹部疝痛、術後症候群(腰痛など)
説明:本方は、当帰四逆湯証で、内に久寒あり(久しく体内が冷えている)ものに、呉茱萸、生姜を加えて用いるもの。大塚敬節氏は、本方の適応証に、疝気症候群のあることを提唱した。
- 十全大補湯
目標:諸種の病後、術後や慢性病、老人や幼児など、体力、気力ともに低下した人、衰弱。疲労しやすく、精神不安、食欲不振の傾向がある場合。皮膚が乾燥し、時に貧血、盗汗、微熱、口乾、めまい、頻尿ないし残尿感を訴える。腹部は一般に軟弱。
応用:慢性疾患および手術後の体力低下、諸種重症疾患および諸種感染症による体力低下(急性増悪期および急性期をのぞく)
説明:四君子湯と四物湯の合方に黄耆と桂枝を加えたもの。和田東郭は、本方の症状に血便、血尿、下腹痛、脱肛、陰茎瘙痒をあげ、疎註要験には、産後や結核の衰弱、貧血、内症による皮膚発疹、慢性の下痢症をあげている。
- 苓甘姜味辛夏仁湯
目標:体力がやや低下し、冷え性で貧血性の人。喘鳴、喘咳、息切れ、水様鼻汁、浮腫などがある場合。脈は浮んで弱く、腹部は軟弱で心下部に振水音を認める。病人が陰虚証で、麻黄剤を用いられず、小青竜湯などを用いると、かえって疲労感が増してくるいが悪くなるようなものによい。
応用:急性気管支炎、慢性気管支炎、気管支喘息、肺気腫
説明:本方の薬物は、甘草以外はすべて利水剤で、水毒を去る効果がある。大部分がいわゆる温薬で構成されているところが、本方の特徴である。
陰証
虚証タイプ(体力が低下している場合)
- 麻黄附子細辛湯
目標:体力の低下した人。体質虚弱の人。少陰病の初期、数日間で、顔色蒼白で悪寒が多いが、時として発熱、熱感もあり、手足が冷えて、倦怠感、軽度の咽頭痛を伴う。慢性症では、冷え症で顔色が悪く、四肢・関節痛、咳嗽、脈は沈細で力がないが、急性症では、浮弱のことがある。
応用:虚弱者や老人の感冒、流感、気管支炎、肺炎
説明:本方は、少陰病で表熱裏寒のものに用いる。この際の熱は仮の熱で、これを真寒仮熱といい、脈が沈んで力のないものである。このとき、太陽病と誤って発汗剤を用いてはならない。
まとめ
花粉症の漢方+鍼灸治療において、患者の証(体力、症状、体質)に基づいて、これら10種類の処方から最適なものを選択します。実証から虚証まで、また各種の症状の特徴に応じて、最も適した処方を選択することが重要です。特に、表証・裏証の見極めや、体力の程度による使い分けが治療効果を左右する重要な要素となります。