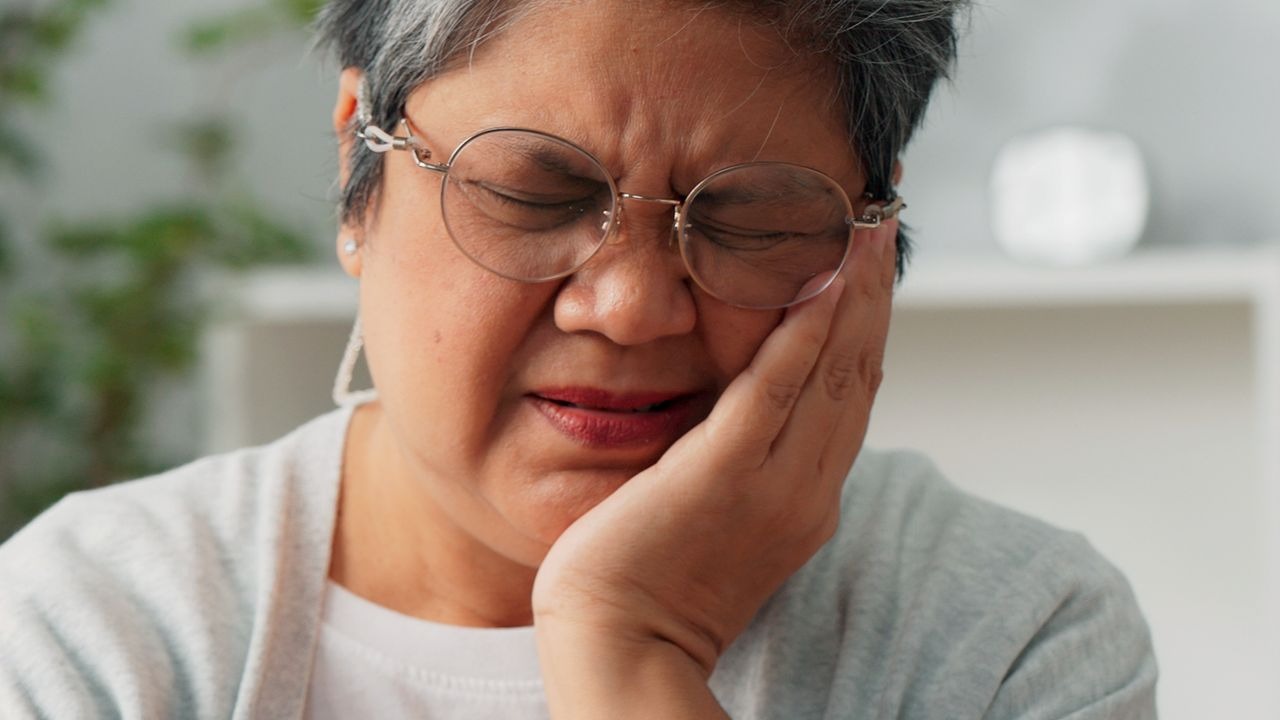こんなお悩みありませんか?
腰痛や肩こりなどの慢性的な痛みを抱えていませんか?そしていつの間にか、音がうるさく感じる、光がまぶしい、匂いに敏感になった——そんな変化に気づいていませんか?夜も眠りが浅く、睡眠薬が手放せない。ストレスに対してとても傷つきやすくなった。これらの症状は「脳過敏症」のサインかもしれません。
動画解説
本記事では、脳過敏症(中枢感作)の原因から、自宅でできる4つの睡眠改善法、そして鍼灸治療で使用するツボまで、動画の内容をさらに詳しく解説していきます。
なぜ脳過敏症が起こるのか?その根本原因
脳過敏症は、単なる「神経質」や「気のせい」ではありません。その背景には、脳の炎症という明確なメカニズムが存在します。特に慢性的な痛みを長期間抱えている方は、脳に老廃物が蓄積しやすく、それが脳過敏症や将来の認知機能低下につながる可能性があります。
現代医学から見た原因
脳過敏症の背景には「アミロイドβ」という脳の老廃物の蓄積があると考えられています。アミロイドβは認知症の原因物質としても知られていますが、実は40代頃から少しずつ脳に溜まり始めます。
- 慢性痛との関連:腰痛、肩こり、顔面痛、帯状疱疹後神経痛などの慢性的な痛みを抱えている方は、アミロイドβが蓄積しやすい
- 脳の炎症反応:溜まった老廃物を処理しようと脳が頑張り、炎症状態が続く
- 過覚醒状態:炎症が広がることで脳が過敏になり、音・光・匂いに対する感受性が異常に高まる
- 認知機能への影響:この状態が続くと、70代以降に認知機能の低下が起こりやすくなる
東洋医学から見た根本原因
東洋医学では、脳過敏症を「心神不安」「肝火上炎」「腎虚」などの観点から捉えます。
- 心神不安:心(こころ)の気が乱れ、精神活動が安定しない状態。不眠や過敏症状として現れる
- 肝火上炎:ストレスや怒りにより肝の気が上昇し、頭部に熱がこもる。イライラや感覚過敏を引き起こす
- 腎虚:生命エネルギーの根本である腎が弱まり、脳を滋養できなくなる。慢性疲労や老化現象と関連
- 気血の滞り:慢性痛により気血の流れが悪くなり、脳への栄養供給が滞る
症状改善への具体的なアプローチ
脳過敏症を改善するカギは「睡眠」です。深い睡眠に入ることで、脳に溜まったアミロイドβなどの老廃物が排出されます。しかし、脳過敏の状態になっている方は眠れなくなっていることが多く、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤を服用しているケースも少なくありません。問題は、ベンゾジアゼピン系の薬は筋弛緩作用がメインであり、深い睡眠を促す効果は限定的なため、脳の老廃物排出が十分に行われないことです。
今すぐできるセルフケア
睡眠改善①:光のコントロール
睡眠改善の中で最も重要なのが「光」です。実に睡眠の質の95%は光のコントロールで決まると言っても過言ではありません。
- 朝の光を浴びる:目の奥にある時計遺伝子が光を感知し、15時間後に睡眠スイッチが入る。朝7時に光を浴びれば夜10時に眠くなる
- 必ず外で浴びる:室内では紫外線量が不足するため、窓越しではなく外に出て浴びることが大切
- アイマスクの活用:夜眠るときにアイマスクをすると、さらに睡眠の質が向上する
- スマホの光は気にしすぎない:太陽光に比べれば影響は小さいので、朝の光を浴びることを優先する
睡眠改善②:血糖値のコントロール
血糖値を緩やかに下げることで、スムーズに入眠できるようになります。
- 夕食で炭水化物をしっかり摂る:食後の緩やかな血糖低下が入眠を促す
- 就寝30分前に蜂蜜をなめる:蜂蜜は安定した構造を持ち、体内での吸収に時間がかかるため、血糖値を緩やかに下げる効果がある。スプーン1杯で十分
- 砂糖は避ける:砂糖は急激に血糖値を上げ下げするため、かえって覚醒を招く
- 果物は食前に:果物に含まれる果糖は血糖値を乱高下させやすいため、食後ではなく食前に摂る
睡眠改善③:後鼻漏の改善
鼻の詰まりや後鼻漏があると睡眠の質が大きく低下します。改善には「ミューイング」という舌のエクササイズが効果的です。舌を上顎に押し当てることで、鼻の奥の血行を改善し、後鼻漏の症状を緩和します。詳しいやり方は後鼻漏に関する別の動画で解説していますので、そちらをご参照ください。
睡眠改善④:頭を冷やす
脳過敏の状態にある方は、自覚がなくても頭に熱がこもっています。
- アイスノンで頭を冷やす:氷枕や冷却ジェルシートを使って頭を冷やしながら眠ると、脳の炎症が鎮まりスーッと眠りに入れる
- 脳過敏の方は気持ちいいと感じる:通常は冷たく感じるアイスノンも、脳に熱がこもっている方には心地よく感じられる
- 深部体温の低下:頭を冷やすことで深部体温が下がり、睡眠の質が向上する
効果的なツボ押し
自宅でのセルフケアとして、以下のツボへの刺激が効果的です:
- 水泉(すいせん):内くるぶしとかかとの間にあるツボ。腎を補い、脳を滋養する
- 陰陵泉(いんりょうせん):膝の内側、すねの骨の際にあるツボ。水分代謝を改善し、むくみや倦怠感を解消
- 肩井(けんせい):肩の中央、首と肩先の中間点にあるツボ。肩こりの改善だけでなく、全身の緊張を緩める
専門的な鍼灸治療のアプローチ
木もれび鍼灸院では、脳過敏症に対して独自のアプローチを行っています。
原始反射の解除
人は生まれた時に「原始反射」という生存のための反射を持っています。本来は3歳頃に消失しますが、ストレスや脳の炎症によって20代、30代以降に再び活性化してしまうことがあります。この原始反射が再覚醒すると、体は常に緊張状態となり、脳過敏や中枢感作を悪化させます。
使用するツボ
- 水泉(すいせん):足の内側、腎経のツボ
- 陰陵泉(いんりょうせん):膝下内側、脾経のツボ
- 横骨(おうこつ):下腹部、腎経のツボ
- 膈兪(かくゆ):背中、第7胸椎の横にあるツボ
- 肩井(けんせい):肩上部のツボ
治療上の注意点
脳過敏や中枢感作の方に対しては、頭部への直接的な刺激は避けるべきです。頭に鍼を打ったり、強いマッサージをすると、かえって過緊張・過覚醒状態を招いてしまいます。当院では、体幹部や四肢のツボを使い、間接的に脳の炎症を鎮める方法を採用しています。
患者様からよくいただくご質問
Q1: 脳過敏症は病院で診断してもらえますか?
A: 「脳過敏症」という診断名は日本独自のもので、海外では「中枢感作(Central Sensitization)」と呼ばれています。明確な医学的定義がまだ確立されていないため、病院で診断を受けることは難しい場合があります。しかし、脳の炎症という観点から捉えることで、適切なアプローチが可能になります。
Q2: 睡眠薬を飲んでいても、紹介された方法は効果がありますか?
A: はい、睡眠薬を服用中の方にこそ実践していただきたい方法です。ベンゾジアゼピン系の薬は入眠には効果がありますが、深い睡眠を促す作用は限定的です。4つの睡眠習慣を身につけることで、薬だけでは得られない質の高い睡眠を目指せます。ただし、薬の減量・中止は必ず主治医と相談の上で行ってください。
Q3: 慢性痛がなくても脳過敏症になることはありますか?
A: はい、強いストレスや心理的な負担が長期間続くことでも脳過敏症は発症する可能性があります。慢性痛が最も有力な原因とされていますが、ストレス環境から身を守ることも重要な予防策です。
まとめ:健やかな毎日を取り戻すために
脳過敏症(中枢感作)は、決して「気のせい」ではありません。脳の炎症とアミロイドβの蓄積という明確なメカニズムに基づいた症状です。
- 慢性痛を放置すると、脳にアミロイドβが蓄積し、脳過敏症や認知機能低下のリスクが高まる
- 深い睡眠を獲得することで、脳の老廃物を排出できる
- 光・血糖値・後鼻漏・頭の冷却の4つの習慣で睡眠の質を改善できる
- 鍼灸治療では原始反射を解除し、脳の過緊張状態を緩める
- 慢性痛やストレスは早めにケアすることが、将来の認知症予防にもつながる
一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。あなたの症状に最適な治療プランをご提案いたします。
木もれび鍼灸院でのご相談・治療をお考えの方へ
当院では、一人ひとりの体質や症状に合わせたオーダーメイド治療を行っています。脳過敏症・中枢感作でお悩みの方、慢性痛を根本から改善したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
【こんな方におすすめ】
- 音・光・匂いに過敏で日常生活がつらい方
- 慢性的な痛みが続いている方
- 睡眠薬を減らしたい・やめたい方
- 頭鳴り・耳鳴りでお悩みの方
- 認知症を予防したい方
- 薬に頼らない体質改善を目指したい方
https://komorebizhenjiu.com/contact
※初回の方には詳しい問診とカウンセリングを行います
※症状や体質について気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください